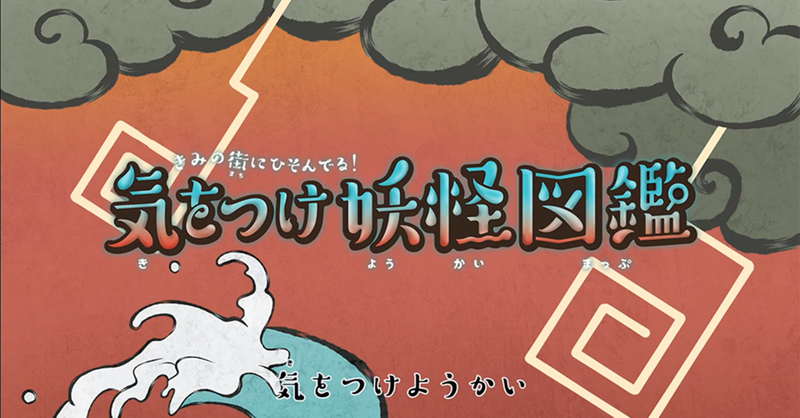── そもそも、水害ハザードマップとはどんなものなのでしょうか?
地域の水害リスクや避難場所などの情報を提供している地図のことです。近年、大規模な水害が頻発するようになったことから、2020年には賃貸契約をする際に、不動産会社からの水害リスク説明が義務化されました。こうした動きを受けて、以前よりはハザードマップを知っている方も増えてきたようです。
とはいえ、そうした引っ越し等のタイミングでしか意識する機会がないとも言えます。恥ずかしながら僕自身、国土交通省の案件を担当するまでハザードマップを見たことがありませんでした。名前を知っている人は多いのですが、普段はなかなか興味関心が持てない。災害が身近に迫らなければ重要性に気づきづらいという課題がありました。
特に若年層は学校教育の中でハザードマップに触れる機会が少なく、閲覧経験の統計を見ると、20〜30代の割合が低く、十分には知られていないということがわかりました。そのため若い世代をメインターゲットに設定。堅いテーマをできるだけ簡潔にわかりやすく、ターゲットにとって親和性の高い企画にすることを目指しました。
── 企画提案するにあたって意識したことはありますか?
今回はハザードマップの重要性を理解する、その入口となる動画を作ることがポイントでした。そこで視聴者の興味・関心を喚起するために、単なる情報ではなくコンテンツとしての価値を追求することを重視しました。動画を見た人が周りの人に紹介したくなり、どんどん波及していくようなコンテンツにしたかったんです。
── 具体的にはどんな企画を提案したのですか?
たとえば、誰もが知っているエピソードを切り口に、間口を広めるという考え方から、童話の「3匹の子豚」を下敷きにした水害のケーススタディ動画。他にも、ハザードマップを教育系YouTuberに解説してもらう案など、オーソドックスなものからチャレンジングな企画まで、5案を提案しました。
「気をつけ妖怪図鑑」もその中のひとつで、企画のポイントは、親子や友人同士で一緒に見ながら水害について理解を深められること。また、キャラクターをメインにすることで、学校やご家庭での教材活用なども想定しています。将来的な展開まで設計しており、なおかつ若い世代に楽しんでもらえると強くイメージできたことが評価され採用となりました。
僕としては、妖怪図鑑は5案の中でも攻めた案だったので、採用していただいて正直驚きました(笑)。でも実は、毎回そういう企画が採用されている気がして、従来の発想にはない部分を期待してもらっているのかなと思います。
現実とアニメーションを融合させることで伝えたかったこと

── どうやって水害を妖怪キャラクターにしていったのでしょうか?
「大雨によって引き起こされる危険を妖怪化する」というコンセプトでキャラクター設計を進めました。
大きくは住宅と街や河川の水害をモチーフにしているのですが、実は「住宅の浸水」という水害をひとつとっても、その段階によって扱いが違います。例えば床下の浸水は、水がちゃぷんと溜まっている程度なので「ちゃぷん小僧」。それが1階の天井までの浸水だったら「びっちゃり親方」。2階の天井までだったら「どっぽん入道」など、危険度に合わせて妖怪のバリエーションを作りました。
住居以外では、河川の氾濫を妖怪化した「はんらんぼう」。また交差する鉄道や道路などの下を通過する低い道路は「アンダーパス」といって大雨の時に水が溜まるのですが、そのアンダーパスに潜む妖怪「みずあつめ」など、かなりの数の妖怪を提案しました。その中から現在の動画に残っている妖怪たちに取捨選択されていきました。

── キャラクターのデザインはどうやって決めたのですか?
特徴の異なる3人のイラストレーターさんをクライアントに提案しました。その中で、東京モノノケさんというイラストレーターの方のタッチが子ども世代から人気が出そうな可愛い雰囲気と、若者を含めた幅広い層に受け入れられるリアルさのバランスがよかったのでおすすめしたところ、受け入れてくださいました。
── 撮影ではどんなことが大変でしたか?
1日で2バージョンを撮影しなければならなかったのが大変でした。「小学生篇」は千葉県の学校をスタジオとして使ったのですが、雨を降らさなけれいけないのに当日すごく晴れていたんです(笑)。教室の窓ガラスに暗幕を貼って薄暗くしてから水を降らせるという手の込んだ仕掛けをしました。

その撮影が終わってから、神奈川県に移動して「大学生篇」の撮影を開始。順調に進んでいたのですが、夜の11時ごろに大きめの地震が起きてハウススタジオがピンポイントで停電するトラブルに見舞われました。最後の1カットの撮影だけが残っていたので、最終的に非常用の電源を使って何とか終わらせることができました。
── 大変でしたね、妖怪が邪魔をしたのかと思ってしまいます(笑)。動画の他にはどんなものを制作したのですか?
地元の市役所や、将来的には学校にも配布して認知してもらえるよう、ポスターやチラシも作らせていただきました。若い人たちが見た時に「何これ?」と興味を持ってもらえるように、妖怪キャラクターを全面に出したクリエイティブにしています。また、興味を持続したままムービーを見てもらいたかったので、QRコードから動画に飛べるようになっています。

── ポスターやチラシを制作する過程ではどんなところにこだわったのですか?
コピーは僕が全て書いたのですが、細かく作りこんだ妖怪の背景設定も入れました。クスッと笑ってもらいながら水害についても学べる、そういった文面になるように心がけて作りました。
ですので、興味の入口としてだけでなく、子どもたちが動画を見た後に、その学校の掲示板に貼られているポスターやチラシを見て「あの妖怪にはこんな設定あったんだ」とさらに理解を深めてもらえるとうれしいですね。
── 設定がしっかりしているからこそ、キャラクターとして魅力的なんですね。「気をつけ妖怪」のテーマソングも印象的でした。
シンプルだけど皆が歌いたくなる、昔流行った「だんご三兄弟」のような歌を意識しています。最初に上がってきた音源から何度もリテイクを重ねて、皆が口ずさめる様なリズムに仕上げました。「小学生篇」と「若年層篇」で、曲のアレンジも変えているので、ぜひ聴きくらべていただきたいですね。
── 制作を進めるうえで、特にこだわった部分などありますか?
現実とアニメーションの境界をなくしていくことで「水害はハザードマップという紙の上だけじゃなく、現実に起こるんだよ」と表現することです。まず最初に実写でそれぞれのターゲットが妖怪について語る中に、その妖怪たちが登場。現実世界から始まり、アニメーションが侵食していくことで、水害を自分事として認識してもらえる仕掛けにしています。

大学生篇の映像では、ホラーチックな会話に合わせて、雨の日の夜に窓の外から妖怪が覗いているなど、まさに「妖怪が出る」感じを演出しています。

この工夫は、面白おかしく見られる動画というだけではなく、ハザードマップへの興味関心を持ってもらうという目的をしっかりと押さえるために、特にこだわったところです。
面白いだけではダメ。課題解決に対する打ち手だからこそ響く
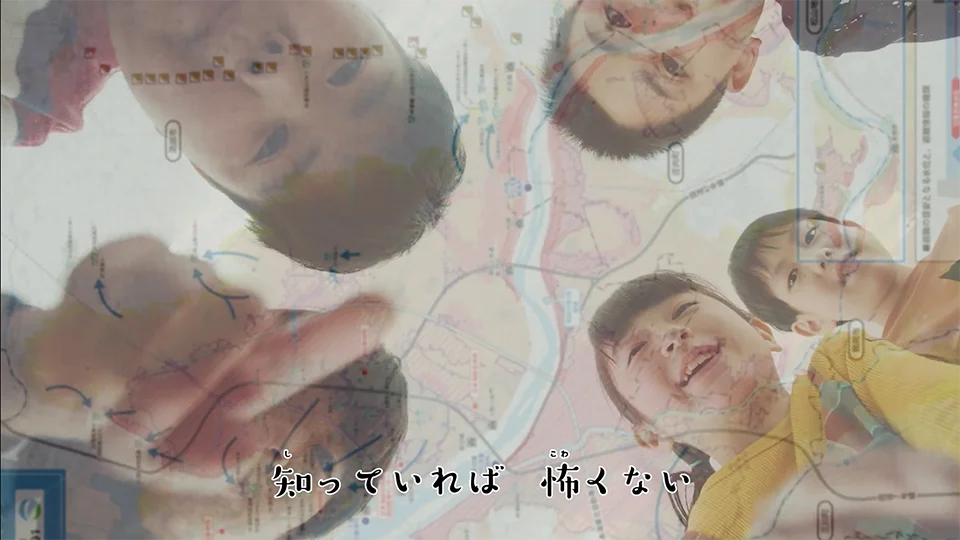
── 動画の公開後、周囲の反応はいかがでしたか?
視聴者からのコメントでは「妖怪が可愛い」「うちの子どもにも見せたい」「小学校の防災担当なので使ってみたい」などのコメントをいただいています。特に親世代から「子どもに伝えやすい」と非常にいい反応が多かったです。
クリエイティブに関しては国交省の方にも評価していただきました。今後はさらに世の中に広げるための施策として、広告も含めたコミュニケーションのプランも提案していきたいと思います。
── 今回のクリエイティブで、特に意識されたことは?
堅いテーマだからこそ、コンテンツとして楽しめるようにということを大事にしていました。そこがぶれなかったことで、社内でも「一般的な啓発動画の常識的な部分を破ったことで、すごくいいものに仕上がった」という意見で一致しています。
── セイタロウデザインは、新しいアイデアや無難じゃないクリエイティブを求めている時に相談できる会社になっているのだなと感じます。
水防団のムービーや、法務省の刑務官募集のためのポスターなど、省庁関連の案件はいくつかやらせてもらってきて、ありがたいことにどれも高く評価していただいています。そういった信頼関係から、今までと違うアプローチをしたい案件で声をかけていただく機会が多いのかもしれません。
── その信頼関係を築けたポイントは何だったのでしょうか。
「国の案件だから」と無難な案ばかり出すのではなく、クリエイティブの立場から「これがいい」と思うものを忌憚なく提案する会社として評価いただけているのだと思います。
その上で、新しい表現に挑戦しながらも、課題解決という目的はぶらさず、クライアントと認識を揃えて進められる。そのバランス感覚も大きいのではないでしょうか。
今回も、課題をクリアするためになぜコンテンツ的な発想が必要なのか、将来的な展開も含めて最初の提案資料の段階でしっかりとご説明し、企画段階での意識のすり合わせも丁寧に行いました。
こういった提案と意識の共有の繰り返しが、結果や反響にも結びついてきたからこそ、飛躍した案を出しても信頼して、選んでいただけたのだと思います。